目次
就労選択支援とは
「就労選択支援」は、障害のある方がこれから働くとき、あるいは今の働き方を見直したいときに、「どんな働き方が自分に合っているか」を丁寧に確かめ、そのうえで最適な就労支援サービスや職場を選べるように支援する制度です。 (厚生労働省)
制度の目的
- 利用者が「自分の特性・希望・能力」をよりはっきり理解できるようにすること
- ミスマッチ(働く場所や支援内容が合わないこと)を減らし、働き続けやすい環境を選ぶことができるようにすること
- 利用希望段階で複数の選択肢を比較できるようにして、「どの支援サービスがよいか」「一般就労に向けてのステップはどれか」を見極めやすくすること
対象となる方/利用条件
| 状況 | 対象になるかどうか | 備考 |
|---|---|---|
| 新たに 就労継続支援B型 を利用しようとする方 | 原則、就労選択支援の利用が必要 | 2025年10月から |
| 新たに 就労継続支援A型 を利用希望の方 | 将来的に原則必要になる(2027年4月から) | 現段階では「希望する場合」などの扱いのケースもあり |
| 就労移行支援 を利用中または検討中の方 | 利用希望・更新時などで関係する | 状況により異なる |
| 特別支援学校等に在学中で、将来の進路に就労支援を考えている方 | 利用可能 | 働き始める前に自分の希望や適性を確認する機会として |
提供される支援内容(流れ・具体的な内容)
以下のようなステップで進みます。支援者・利用者双方が「何をするか」「いつ何を決めるか」をイメージしやすくしています。
- 相談・申請
市区町村の障害福祉窓口、または計画相談支援事業所等で、「就労選択支援を使いたい」という希望を伝え、申請を行います。 (厚生労働省) - アセスメント(評価・分析)
小さな作業体験、観察、面談などを通じて、本人の「できること」「得意なこと」「苦手なこと」「働きたい内容や働き方」「必要な配慮」などを整理します。 - 多機関連携によるケース会議
アセスメント結果をもとに、利用者本人、家族・支援者・相談支援専門員・ハローワークや医療機関・教育関係機関等が関わり、今後どの方向で進むかを話し合います。 - アセスメントシートの作成
評価結果・希望・配慮事項等を整理し、文書化します。これがその後の支援サービス選択・支援計画の基礎資料となります。 (厚生労働省) - 支援サービスや職場の選択・利用開始
アセスメントの結果を踏まえて、以下のような選択肢から最も合うものを選びます。- 就労継続支援B型/A型
- 就労移行支援
- 一般就労への直接移行
- その他、職業訓練や教育機関、地域支援センターなども含め検討可
- 期間と見直し
アセスメント期間は原則1か月以内。ただし、必要があれば最長2か月まで延長可能です。
支援を開始した後も、希望や状況が変われば見直しが可能です。
利用の流れの例(具体例)
利用者さんの例で「働き方を見直したい・これからB型の利用を考えている」ケースを想定すると、こんな流れになります。
例:Aさん(仮名/35歳/発達障害あり/B型事業所を考えている)
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ステップ1 | 障害福祉課または相談支援専門員と面談。「B型を使いたいけれど、自分に合っているだろうか?」という不安があることを伝える。 |
| ステップ2 | 就労選択支援を申請。支給決定を受ける。 |
| ステップ3 | アセスメントが始まる(約4週間以内)。作業体験として、軽作業/パソコン入力/清掃などを少しずつ試してみる。面談で「集中しやすい時間帯」「苦手な仕事環境(騒音・人との接触など)」について聞いてもらう。 |
| ステップ4 | ケース会議を行い、Aさんの得意な点(丁寧さ・集中力がある)、配慮が必要な点(疲れやすい・大きな音が苦手)、希望(静かな環境で、単純作業中心、定時帰宅重視)などを整理。 |
| ステップ5 | アセスメントシートが完成。これをもとに、B型の事業所を見学したり、別の支援A型・移行支援・一般就労も含めた選択肢を提示してもらう。 |
| ステップ6 | 最終的にB型を利用開始。利用開始後も、「もっとチャレンジしたい」「別の働き方を試してみたい」という希望があれば、再度見直す。 |
支援者(事業所・相談支援員等)のポイント
- アセスメントを丁寧に行うこと(希望・特性を丁寧に聴く/観察をする)
- 多機関連携を大切にすること(医療・教育・ハローワーク等との連携)
- 情報提供をしっかり行うこと(選べる支援サービスの種類・働き方の実際の様子・配慮事項など)
- 利用者が納得できるよう、選択肢を見える形で提供すること
- 制度開始後の変更にも柔軟に対応できる体制を整えること
制度開始とスケジュール
- 施行日:2025年10月1日から全国でスタート。
- B型を新たに利用する方 については、2025年10月から就労選択支援の利用が原則となる。
- A型や就労移行支援については、順次適用時期が設定されており、全てに原則適用されるようになる予定です。
表/まとめ図(HP掲載用)
就労選択支援の主な流れ
相談・申請 →
アセスメント(作業体験・面談・観察) →
ケース会議(関係機関) →
アセスメントシート作成 →
支援サービスの選択・利用開始 →
見直し
「どの支援サービスがいいか」比較の例
| 支援サービス | 特長 | 向いている人の例 |
|---|---|---|
| 就労継続支援B型 | 雇用契約なし。ゆったりしたペースで働ける。訓練より作業中心。 | 体力や集中が安定しない方、フルタイムが難しい方、まず慣れる段階の方など |
| 就労継続支援A型 | 雇用契約あり。賃金が出る。実績や責任もやや高め。 | 働く時間がある程度とれる、ある程度の作業能力や体力がある方 |
| 就労移行支援 | 一般就労を目指すための訓練・支援、就職活動支援あり。 | 将来的に一般企業で働くことが希望・可能と思われる方 |
※就労選択支援のアセスメントを通じて、どの道がより実際的かを利用者と支援者で一緒に考えます。
当事業所のご案内
当事業所では、精神疾患や発達障害のある方を中心に受け入れ、安心して自分らしく働ける環境づくりを大切にしています。
2025年10月から始まる「就労選択支援」を取り入れ、一人ひとりの希望や特性に合わせて、「自分に合った働き方」 を一緒に見つけていきます。
当事業所の強み
- AIを活用したデザイン・文章作成
最新のAIツール(ChatGPT、Canva、Stable Diffusionなど)を活用し、チラシやポスター、SNS文章などを制作。創造力を活かしながらスキルアップできます。 - 水耕栽培
室内で季節を問わず野菜を育てることができ、農作業が苦手な方でも安心して取り組めます。育てた野菜は地域の方々にも喜ばれています。 - 地域清掃活動
公園や道路の清掃を通じて、地域とのつながりや達成感を得られます。体を動かすことが好きな方にもおすすめです。
当事業所でできること
- 自分の得意・不得意を見つめ直す「アセスメント」
- AI作業や農作業を体験しながら、自分に合った働き方を探す
- 地域との交流を通じた社会参加
- 就労継続支援B型を中心とした働き方のサポート
こんな方におすすめです
- パソコンやデザインに興味がある方
- 自分のペースで働きたい方
- 地域の中で役割を持ちたい方
- 精神疾患や発達障害があり、一般就労に不安を感じている方
お問い合わせ
関連記事
-

首里カルディアが大切にしている「安心して通える環境づくり」
就労する環境で未来は変わる 就労継続支援B型を選ぶうえで、作業内容と同じくらい大切なのが**「安心して通えるかどうか」**です。 首里カルディアでは、✔ 無理に会話を… -


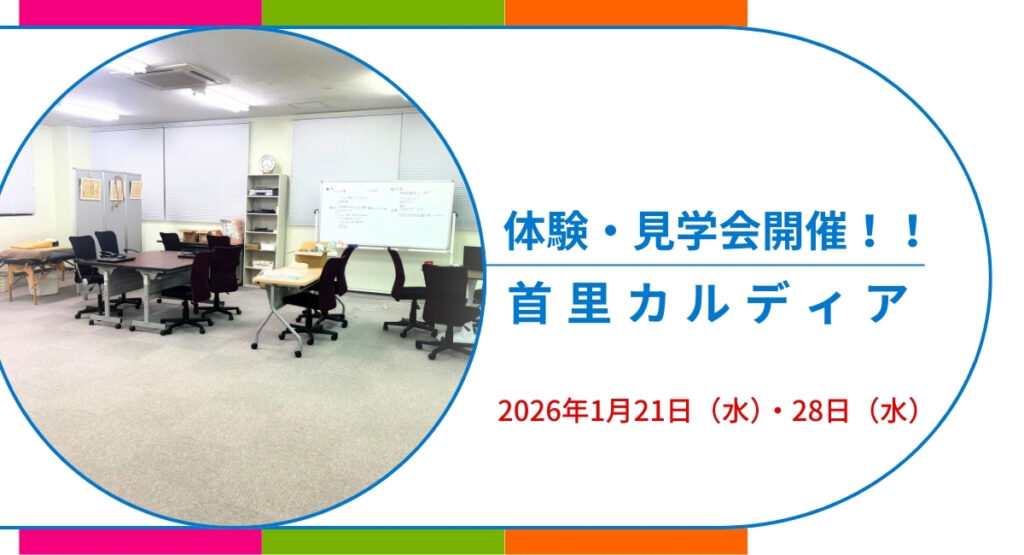
【無料体験会開催】整体とITを学べる就労継続支援B型「首里カルディア」体験会のご案内
楽しんで学べる 「就労継続支援B型って、実際どんなところ?」「自分に合う作業や環境か、一度見てから考えたい」 そんな方のために、首里カルディアでは無料体験会を開… -



首里カルディアの1日の流れ|就労継続支援B型の過ごし方
一日楽しく作業をしていく 首里カルディアのブログをご覧いただきありがとうございます。 「就労継続支援B型って、1日どんな風に過ごすの?」そんな疑問をお持ちの方へ… -



首里カルディアは「ご家族と一緒に支える」就労継続支援B型です
首里カルディアのブログをご覧いただき、ありがとうございます。 「子どもが続けられるか不安」「体調や気持ちの波が心配」 就労支援を考えるとき、ご家族の不安はとて… -



首里カルディアのスタッフ体制とサポートについて
安心して作業ができる環境作り 首里カルディアのブログをご覧いただきありがとうございます。 「どんなスタッフがいるの?」「ちゃんとサポートしてもらえる?」 そんな… -


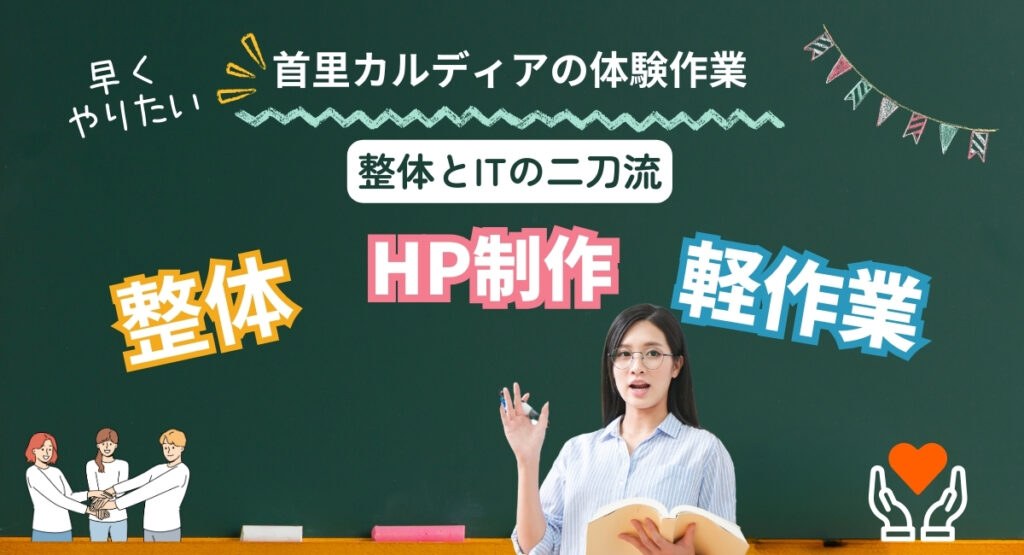
首里カルディアで体験できる作業内容をご紹介します
自分のペースでできる作業 首里カルディアのブログをご覧いただきありがとうございます。 今日は、首里カルディアで体験できる作業内容についてご紹介します。 パソコン… -


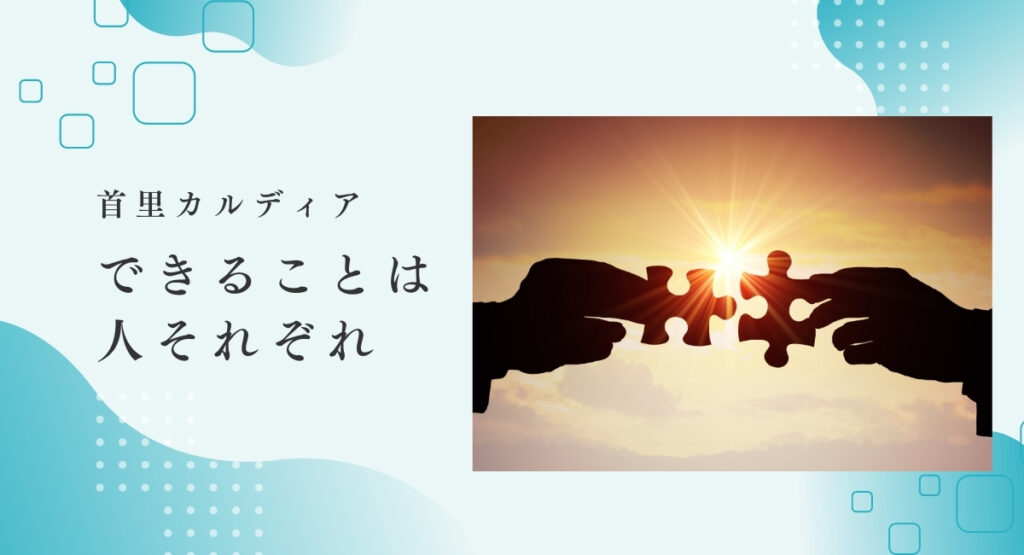
「できることは人それぞれ」首里カルディアの考え方
自分のペースでゆっくりと 首里カルディアのブログをご覧いただき、ありがとうございます。 今日は、首里カルディアが大切にしている考え方についてお話しします。 「で… -


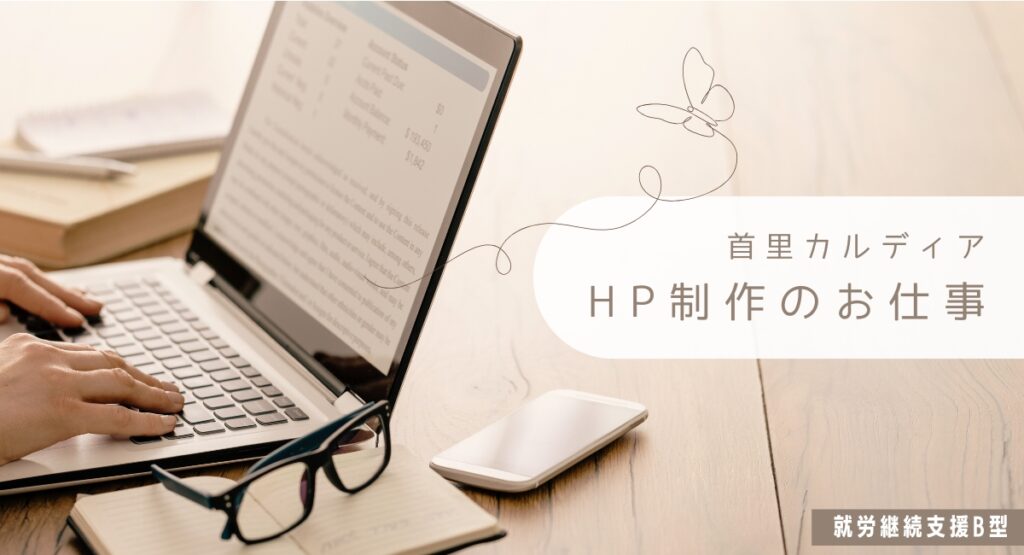
那覇市首里の就労継続支援B型|首里カルディアで学べる「HP制作」の仕事とは?
パソコン作業のスキル 「パソコンを使った仕事に興味がある」「将来につながるスキルを身につけたい」「体力に自信はないけど、何か始めてみたい」 そんな思いをお持ち… -


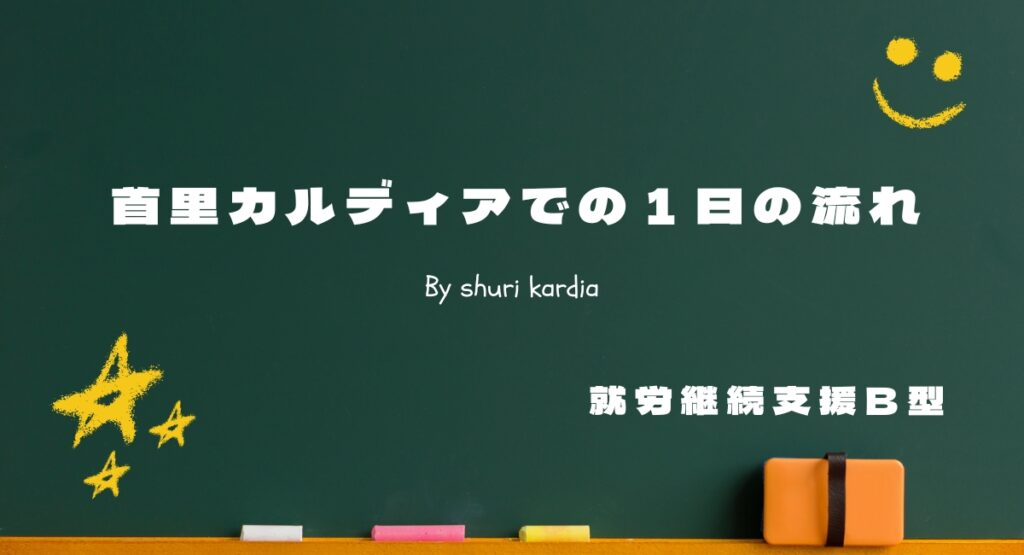
首里カルディアでの1日の流れ
無理なく、自分のペースで通える場所 首里カルディアのブログをご覧いただき、ありがとうございます。那覇市首里にある就労継続支援B型事業所 首里カルディアです。 「B… -



【ご家族様へ】
那覇市首里の就労継続支援B型|首里カルディアが「安心して通える理由」 「就労継続支援B型を探しているけれど、本当にこの子(家族)が通い続けられるだろうか…」 そん… -


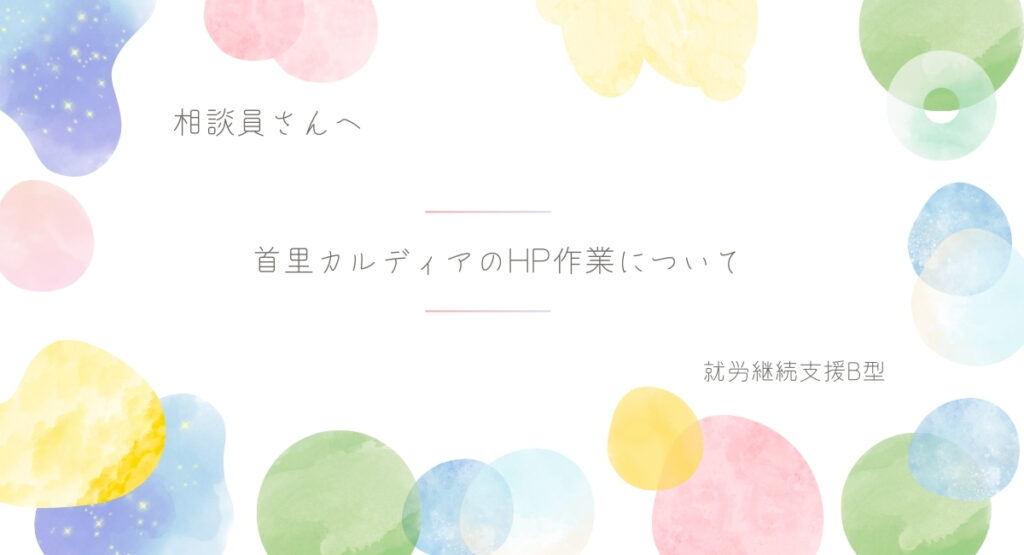
【相談支援専門員の皆さまへ】
首里カルディアのパソコン作業(HP制作)について 就労継続支援B型事業所 「首里カルディア」では、パソコン作業の一環としてホームページ制作業務に取り組んでおります… -


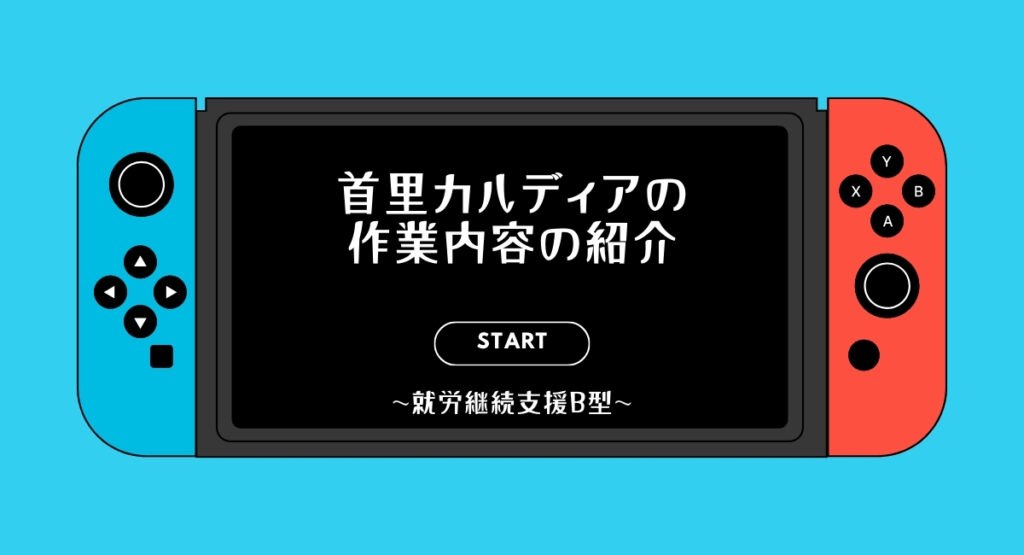
首里で安心して通える就労継続支援B型。首里カルディアの作業内容をご紹介します
🌿 首里で安心して通える就労継続支援B型 〜首里カルディアの作業内容をご紹介します〜 おはようございます。首里カルディアです。当事業所は、那覇市首里にある就労継… -


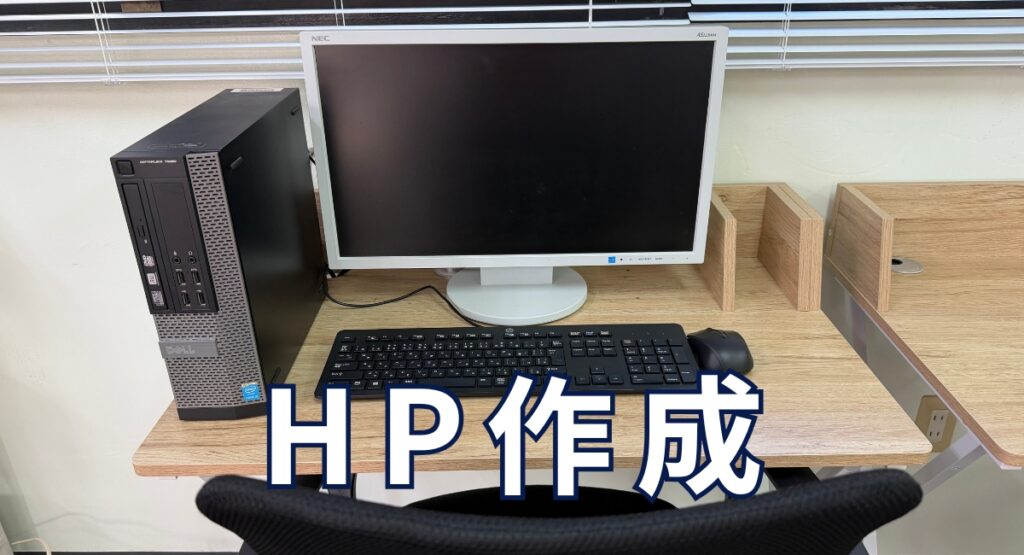
🌿 首里カルディアのパソコン作業
〜みんなで取り組むHP(ホームページ)制作〜 首里カルディアでは、パソコンを使ったお仕事の一つとして、HP(ホームページ)制作に取り組んでいます。 「ホームページ… -


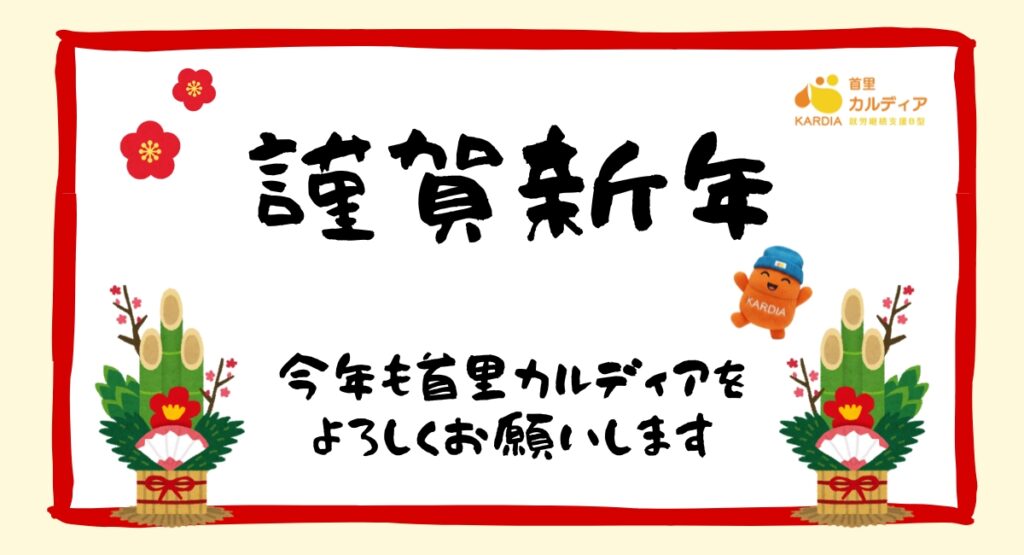
新年のご挨拶
🎍新年のご挨拶🎍 あけましておめでとうございます。旧年中は、利用者の皆さま・ご家族の皆さま・関係機関の皆さま、そして地域の皆さまより温かいご支援を賜り、心より… -



🎍 年末のご挨拶
今年もありがとうございました 今年も残すところわずかとなりました。本年は、首里カルディアの活動にご理解・ご協力を賜り、誠にありがとうございました。 干渉波治療… -



🚌 首里カルディアの送迎サービスについて送迎無料
「一人で通うのが不安…」そんな方をやさしくサポートします 首里カルディアでは、通所の負担をできるだけ少なくし、安心して通っていただくために送迎サービスを行って… -


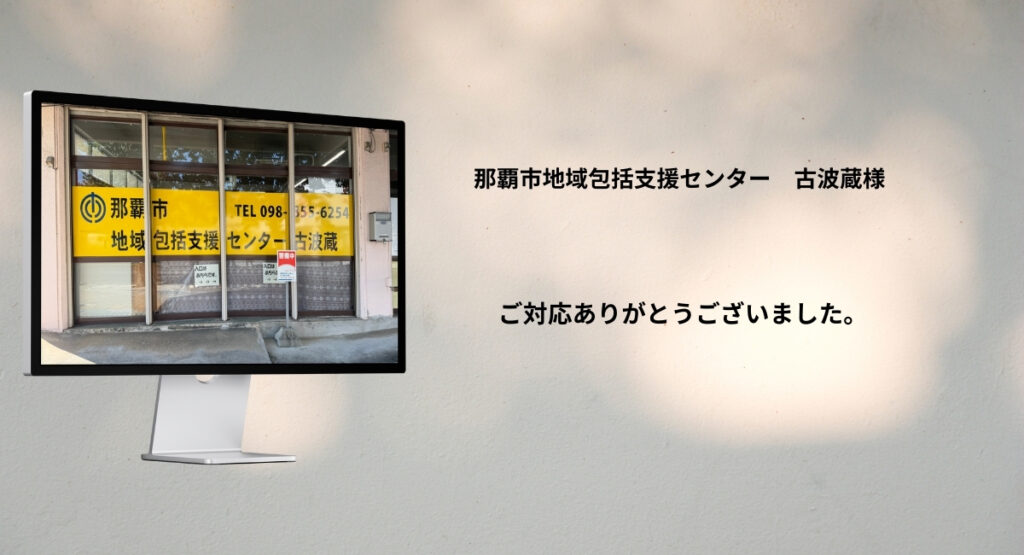
那覇市地域包括支援センター 古波蔵 様
ご挨拶へ行ってきました 先日那覇市地域包括支援センター古波蔵事業所へご挨拶へ行ってきました。 とても親切に対応していただき事業所の案内もさせていただきました。 … -


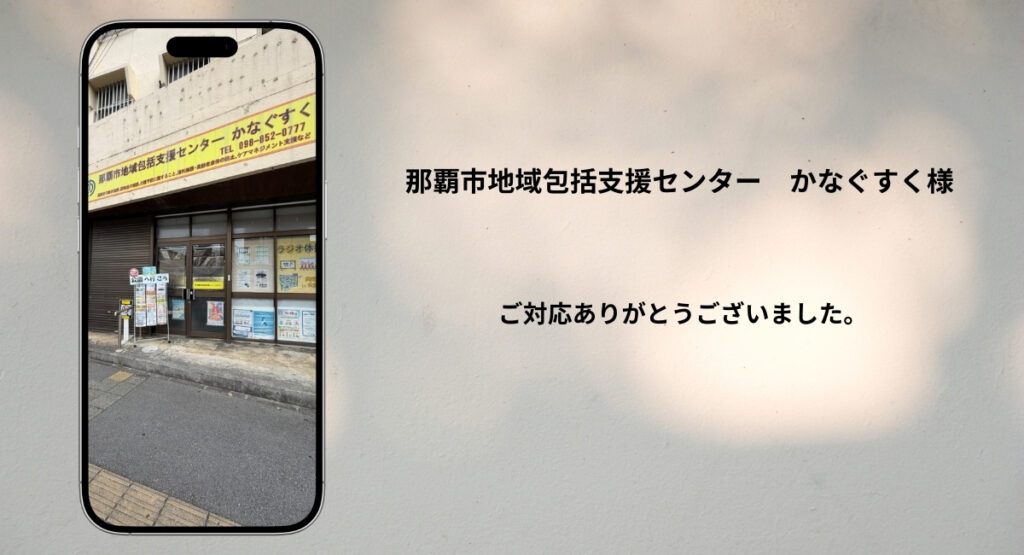
那覇市地域包括支援センターかなぐすく 様
ご挨拶へ行ってきました 先日那覇市地域包括支援センターかなぐすく事業所へご挨拶へ行ってきました。 とても親切に対応していただき事業所の案内もさせていただきまし… -


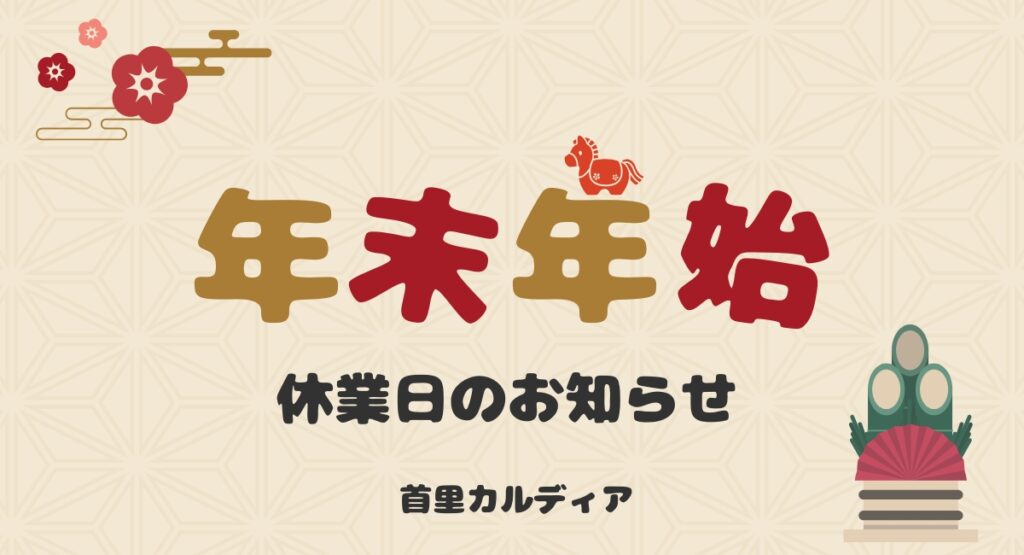
年末年始のお知らせ
年末年始のお知らせ 年末年始の営業のお知らせ年末年始は30日~4日まで休みなっています。 年末年始スケジュール 年始は5日の8時30から営業しています。 今年も… -



お守り太鼓
合格祈願、厄除けにオススメ 首里カルディアの軽作業はお守り太鼓を作っています。 これから新年、受験などで祈願が多くなってきます。 ぜひ首里カルディアでも販売して… -


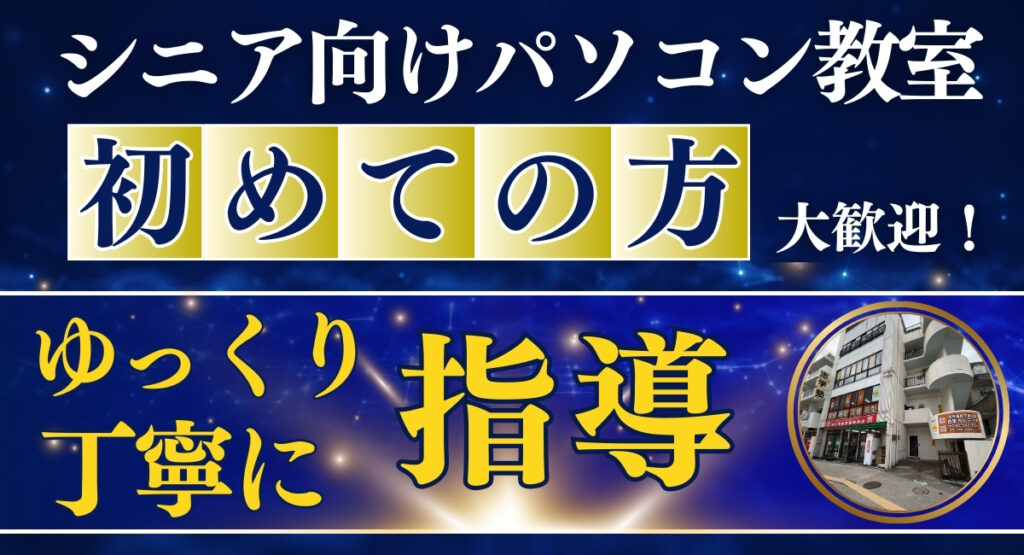
初心者パソコン教室(シニア・一般の方向け)
気軽に通えるパソコン教室 【首里駅から徒歩1分|初心者にやさしいパソコン教室】 沖縄県那覇市首里の就労継続支援B型事業、首里カルディアが「初心者のためのパソコン… -



【NAHAマラソン対策】ランナーが選ぶ“本当に効果を感じる体ケア”
干渉波治療で疲労回復・痛み予防・走力アップ! NAHAマラソンは、真冬とはいえ暑さが残る沖縄特有の気候、過酷なアップダウン、長い沿道の応援を乗り切る必要があるフル… -


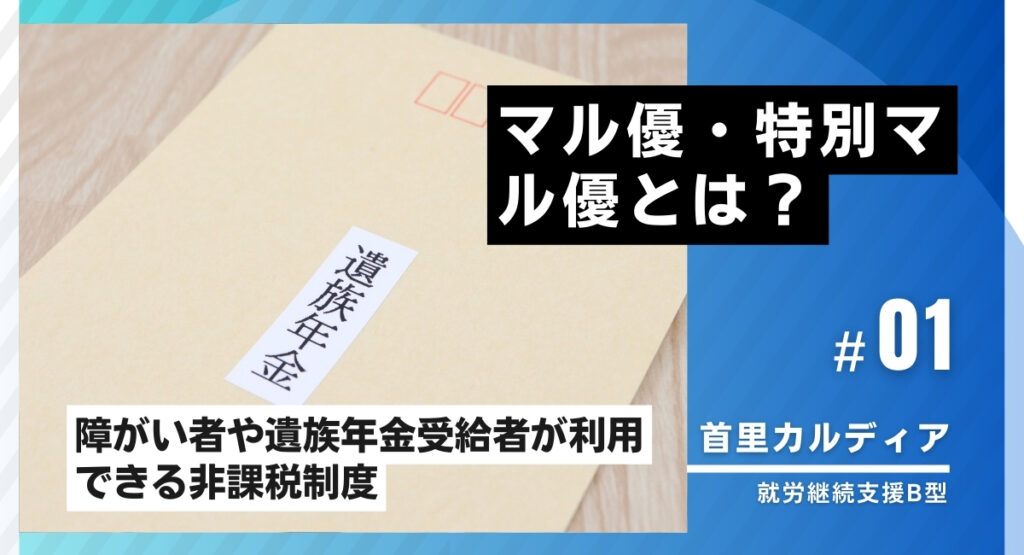
【完全解説】障がい者や遺族年金受給者が利用できる「マル優・特別マル優」とは?非課税でお得に貯蓄する制度
知ってて損はない 障がいのある方や遺族年金を受給している方が利用できる「マル優(障害者等に対する非課税貯蓄制度)」と「特別マル優(遺族年金等受給者に対する非課… -



【保存版】那覇市で身体障害者手帳を取得する方法|申請手続き・必要書類・メリットを徹底解説
■ はじめに 身体障がい者手帳(以下、身体障害者手帳)は、生活をより安心・便利にするための重要な制度です。那覇市にお住まいの方からも「どんな手続きが必要?」「必…







